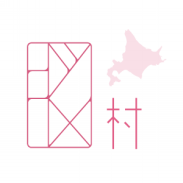2024/03/27 08:00
ほんの少し前まで、にんにくの優れた健康効果は、ほぼアリシンによるものと考えられてきました。
ところが、アリシンの主な作用は抗菌・抗ウィルスになり、それ以外の健康効果はアリシン以外の様々な特効成分によるもの、ということが徐々に解明されてきたのです。
にんにくとにんにく油の違いは何?
それは・・・、含まれている成分の違いになります!

生にんにくの健康増進作用となる成分は「アリシン」、にんにく油の成分は「アホエン」になります。
にんにくはスタミナ源として知られていますが、 これは、にんにくを刻むと発生する臭いの成分「アリシン」の働きによるものです。
この「アリシン」が油に溶け出すことで生成されるのが「アホエン」。 「アリシン」よりも安定性に優れているうえ、 オイルに漬け込んでいるので、強い臭いや刺激性は低くなっています。
にんにくの匂いの元、アリシン
生にんにくの細胞内にある無臭のアリインというアミノ酸の一種と、維管束にあるアリイナーゼという酵素の2つが混ざり合い、分解されることで、特有の匂いを発生するアリシンという化合物に変化します。

このアリシンには、抗菌効果やビタミンB1を吸収しやすくする作用があります。
抗菌効果
にんにくはそのままでは匂いはしませんが、ちょっとキズをつけるだけでも強い匂いを発します。実はこれ、自分の身を守る手段なのです。色々な生物がにんにくを食べようとキズをつけた時、素早く刺激臭を発生させ、外敵を攻撃し、さらにキズを受けた部分を殺菌するのがアリシンの働きとなります。にんにくの殺菌作用の秘密はアリシンなのです。
ビタミンB1の吸収促進
アリシンは、スタミナ源にもなるという働きを持っています。
人は、ビタミンB1が減ってしまうと体がだるくなり、体力が落ちて疲れやすくなり、やる気を失ったり、イライラすることが多くなります。ビタミンB1は、炭水化物を材料にエネルギーをつくり出す過程に欠かすことができない栄養素のため、こういったことが起きてしまいます。
ビタミンB1は、熱に弱くて水に溶けやすく、さらに体内での吸収がしにくいという特徴を持っています。一気にたくさん摂取しても、貯蓄できずに、尿とともに排出されてしまうのです。しかし、アリシンは、ビタミンB1と結びつき、アリチアミンという物質を形成し、ビタミンB1をスムーズに吸収させてくれます。
にんにく油に含まれる、アホエン
アホエンは、アリシンと同じく、天然のにんにくにはほとんど含まれていません。
にんにくを切ったり、すりおろしたものを、植物油やアルコールに漬け込むことではじめて生成される、水に溶けずに油に溶けやすい脂溶性の性質を持つ成分です。つまり、アリインがアリイナーゼの作用でアリシンになり、そのアリシンがある条件のもとで変化してできる、それがアホエンです。
アホエンの生理機能には、次のようなものが挙げられます。
・血小板凝集抑制作用
・肝障害に対する保護効果
・抗菌作用
・抗腫瘍作用
アホエンは、アリシンに比べると安定した成分!
ここに、2つを比べた実験結果を記します。
・アリシンの場合
20℃、20時間保持でほぼ分解される。
・アホエンの場合
ゼラチンを原料としソフトカプセル化したものを25℃で1年間保存しても減少率は20%にとどまり、マイナス20℃で冷凍保存した場合には1年程度の長期間においてほとんど減少しない。
アリシンが不安定なのは、生成された直後から、徐々にスルフィド類へ変化していくためです。
つまり、アリシンを効果的に摂取するには、食べるたびに切ったり、すりおろしたりする必要があるということです。
アホエンを含むにんにく油は、保存性に優れ、取り扱いが簡単!
アリシンは外敵を攻撃する目的で発生しているので、匂いとともに強い刺激があります。
そのため、体に良い作用を持ち合わせていますが、生で食べると胃粘膜を傷つけてしまうことがあるなど多少の副作用を伴ってしまいます。
一方で、アホエンは、油に漬けることで発生するので、強い匂いや刺激が必然的に低くなるのです。
「体に良い様々な効果」があり、「保存しやすい」のがアホエン、にんにく油なのです!
※ 本記事に関する内容は、篠浦伸禎先生の下記書籍より抜粋させていただきました!
#アホエンオイル #ニンニクオイル #ピンクにんにく #にんにく #無農薬栽培 #無化学肥料栽培 #北海道 #千歳市 #脳村 #脳村直売所